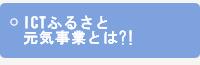
~地域の元気、安全・安心を応援するモデル構築事業~
総務省では、ICTの利活用を通じて地域経済の活性化や少子高齢化など地域が抱える課題の解決を促進するモデル的な取り組みを自治体等の事業への委託事業「地域ICT利活用モデル構築事業」を実施してきた。本会では、本事業を更に展開させるべく『ICTふるさと元気事業』(正式には、平成21年度情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金事業という)の採択を得、医療機関相互情報連携、周産期医療支援、在宅医療支援、ビジュアルコミュニケーション支援、そしてバイタルモニターシステムの5コンポーネントをフレームワークとして有機的に結合し、地域特性に合わせた事業展開を継続している。ちなみに「周産期医療支援システム」は、妊婦さんと赤ちゃんの安心・安全に加え、妊娠から出産まで合計約16万円の交通費を含む費用軽減効果※も実証されており、先進的な遠隔地域医療連携モデルとして注目されている。
※「地域ICT利活用モデル構築事業実施地域における効果検証等に関わる調査」(総務省)
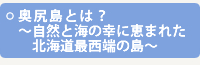
- 面積/142.98平方キロメートル(北海道内離島では利尻島に次ぐ2番目に大きな島。全国では14番目)
- 人口/3640人・1700世帯(平成19年1月末現在。昭和35年のピーク時に比べ50%以上も減少)
- 主な産業/水産業、観光
- 島名の由来/アイヌ語の「イクシュン・シリ」、その後「イク・シリ」と訛ったもの。「イク」は「向こう」、「シリ」は「島」で、「向こうの島」の意味
- 奥尻町ホームページ
http://www.town.okushiri.lg.jp/
奥尻島に見る 「周産期医療支援システム」の現状
妊婦健診も出産も島では不可能 海を越えていた妊婦さんにもたらされた福音

奥尻島から望む北海道

なべつる岩
産婦人科医の不足は全国的な課題だが、北海道はとりわけ深刻で、1996年から2006年の10年間に439人から359人と18.2%も減少。人口10万人当たりの産婦人科医師数は全国平均を大きく下回っている。まして海を隔てた島となれば状況はさらに悪く、奥尻島では産婦人科専門医はゼロ、それどころかフェリーが通う対岸の江差にも分娩できる病院はない。初診から分娩までの6~8カ月もの間、妊婦さんはフェリーや飛行機に揺られるリスクを侵し、幾度も海を越えなければならなかったのである。
医療技術が進歩したとはいっても、妊娠中にはいつ何が起こるかわからない。例えば、赤ちゃんも母体も危険な切迫早産・流産である。
「そんなときは、ヘリコプターで市立函館中央病院まで運ぶしか手はありません。年に何回かは、切迫早産の疑いのある妊婦さんを運ぶお手伝いをしてきました。その時はいつも頑張れよと心から思いましたね」

奥尻町国民健康保険病院 前田看護師長
「私の時代までは分娩施設もあったし、助産師さんもいましたから、妊婦さんはみんな奥尻で出産できました。10年前は札幌医大から月1回、医師が来てくれていたのですが、島の人口が減るにつれてだんだんと減って…。元気な妊婦さんでも妊娠中は不安なもの。何とかならないかなとずっと思っていました」
こうした産婦人科医療過疎に明るい兆しが見えたのは、平成20年2月のこと。北海道の離島としては初めて、「周産期医療支援システム」による『遠隔妊産婦健診』が実施されたのである。