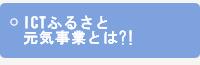
~地域の元気、安全・安心を応援するモデル構築事業~
総務省では、ICTの利活用を通じて地域経済の活性化や少子高齢化など地域が抱える課題の解決を促進するモデル的な取り組みを自治体等の事業への委託事業「地域ICT利活用モデル構築事業」を実施してきた。本会では、本事業を更に展開させるべく『ICTふるさと元気事業』(正式には、平成21年度情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金事業という)の採択を得、医療機関相互情報連携、周産期医療支援、在宅医療支援、ビジュアルコミュニケーション支援、そしてバイタルモニターシステムの5コンポーネントをフレームワークとして有機的に結合し、地域特性に合わせた事業展開を継続している。ちなみに「周産期医療支援システム」は、妊婦さんと赤ちゃんの安心・安全に加え、妊娠から出産まで合計約16万円の交通費を含む費用軽減効果※も実証されており、先進的な遠隔地域医療連携モデルとして注目されている。
※「地域ICT利活用モデル構築事業実施地域における効果検証等に関わる調査」(総務省)
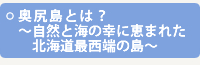
- 面積/142.98平方キロメートル(北海道内離島では利尻島に次ぐ2番目に大きな島。全国では14番目)
- 人口/3640人・1700世帯(平成19年1月末現在。昭和35年のピーク時に比べ50%以上も減少)
- 主な産業/水産業、観光
- 島名の由来/アイヌ語の「イクシュン・シリ」、その後「イク・シリ」と訛ったもの。「イク」は「向こう」、「シリ」は「島」で、「向こうの島」の意味
- 奥尻町ホームページ
http://www.town.okushiri.lg.jp/
奥尻島に見る 「周産期医療支援システム」の現状
あってはならない医療格差を 「見守りの複合体」の拡大で解消する
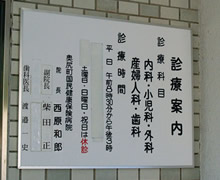
産婦人科と書かれているが、専門医は不在
その第一は、現行の医療制度上の位置づけが不十分であることだ。例えば、「周産期医療支援システム」による妊婦健診は、国や自治体が定義する「妊産婦健康診査」として、未だ認可が得られていない、つまり遠隔健診では、健診項目は「対面」での健診とほぼ同等なのだが、診療報酬の請求はできないのである。奥尻島での「周産期医療支援システム」のケースでは、奥尻国保病院・柴田先生、そして遠藤先生の〝善意=ボランティア〟で成り立っているのが実情である。

奥尻町国民健康保険病院 柴田正副院長
こうした要望を踏まえ、平成22年度に入ると、本会が事業主体となった「ICTふるさと元気事業『北海道南西部・広域医療連携ネットワーク構築事業』」により、地域間で相互に連携が可能で、大幅な機能強化・操作性向上を図った周産期電子カルテ「Hello Baby-Hokkaido」を中心とする道内完結型クラウド・ネットワークが整備され、血圧・体重などのバイタル・モニターやテレビカンファレンスをベースに、超音波診断装置(エコー装置)のリアルタイム画像伝送も実現しており、より診断の精度は高まっている。
ネットワーク・システムや人材に関わることには、解決の道も方策もある。真の問題は、健診費用も含めた解決策が、現状では「周産期医療支援システム」に関わる人びとの努力と熱意に依存していることにあるのではないだろうか。地域医療格差は、決してあってはならないこと。北海道をはじめ産婦人科医の都市部偏在や、周産期医療の空白地域(=赤ちゃんが産めない地域)が全国各地で急速に広がっている現在、奥尻島が実証した「周産期医療支援システム」による「見守りの複合体」を線から面へ、面から更に広域へと拡大していくことは、いま望み得る最も具体的かつ現実的な「答え」に思われるのである。

奥尻から青苗に向かう一本道(道道39号線)

奥尻島の西海岸に咲くアカツメクサ